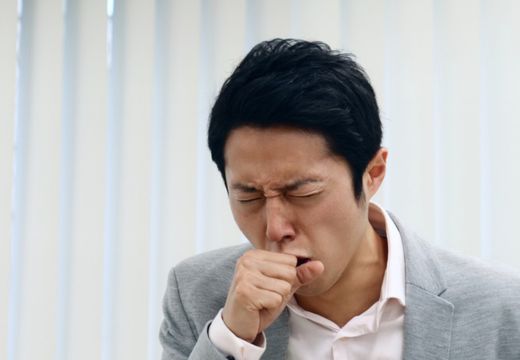
副鼻腔気管支症候群は、鼻の奥にある副鼻腔と、肺へとつながる気管支という呼吸器の上下の通り道の両方で、慢性的な炎症が起きている状態を指します。
代表的には、慢性副鼻腔炎に加えて、長く続く慢性気管支炎やびまん性汎細気管支炎、さらにはびまん性気管支拡張症などの下気道に炎症が同時に見られることが特徴です。
痰を伴う湿った咳が長引くことが多く、マクロライド系の抗菌薬が有効なことが多いため、しつこい咳の原因を探る上で重要な疾患のひとつとなっています。
発症の背景
鼻や気管支には、本来、細菌やウイルスから身を守る防御機能がありますが、それに何らかの障害が起きると、炎症が慢性化しやすくなると考えられています。
ただし、実際のところ、詳しいメカニズムについてはまだ明確にわかっていない部分も多く残されています。
主な症状の特徴
これらは慢性副鼻腔炎によく見られる症状で、鼻水や粘液がのどに絡むことで、咳払いが多くなる傾向があります。寝ているときにのどに鼻水が垂れ込んでせき込み目が覚めることもあります。
- 副鼻腔炎の関連症状
- 鼻がつまる
- のどの奥に鼻水が流れる(こうびろう:後鼻漏)
- においが分かりにくくなる
- たまに頬が押されている感じがしたり、圧痛を感じる
咳が止まらない場合
8週間以上も湿った咳が止まらない場合には、この病気を疑う必要があります。喘息に見られるような息苦しさや「ヒューヒュー」としたぜんめい(喘鳴)、また発作的な呼吸苦はあまり起こりません。
- 長く続く痰のからむ咳
副鼻腔気管支症候群の検査
- レントゲンなどの画像検査で、粘膜の腫れや液体のたまりが見える
- 鼻水や痰の中に、炎症のサインである好中球が増えている
当院ではメディカルスキャニング目黒と連携し副鼻腔CTや胸部CTによるびまん性汎気管支炎やびまん性気管支拡張症の診断を受けることができます
副鼻腔気管支症候群の診断方法
以下の3つが揃っている場合に、この病気の可能性が高くなります。
- 8週間以上続く湿った咳
- 慢性副鼻腔炎に特徴的な症状や画像所見
- マクロライド系抗生物質や去痰薬による改善が見られること
これらの情報をもとに、他の長引く咳の原因(咳喘息、感染後咳嗽など)と区別していきます。
副鼻腔気管支症候群の治療方法
症状の重さに応じて、治療は段階的に行われます。
-
軽症
去痰薬(例:L-カルボシステイン):痰を出しやすくし、気道粘膜の状態を改善
-
気道粘膜潤滑薬(例:アンブロキソール)
末梢気道の乾燥や炎症に対応し痰の粘稠を下げて痰を出やすくしたり、鼻づまりをやわらげたりする作用があります。
-
中等症
少量マクロライド長期療法:通常の抗菌薬の用量の1/4~1/2の量で、抗菌作用より気道の炎症をゆるやかに抑えることを期待しておこなう治療です。
-
重症・悪化したときの対応
適切な抗菌薬の投与:痰の検査で特定された菌に合った抗生物質を選び、1~3週間ほど使用します。効果が
-
副鼻腔の手術
副鼻腔の炎症が強く、薬だけでは改善しない場合には耳鼻科での手術が検討されます。
まとめ
ふくびくうきかんし症候群(副鼻腔気管支症候群)は、長引く湿った咳の背景にあることが多く、そのほかの咳の疾患とことなります。特に、マクロライド系抗菌薬の効果が高いことが知られています。もし、慢性的な咳で困っている場合は、気管支だけでなく副鼻腔も視野に入れた総合的なアプローチが必要ですので一度ご相談ください。





